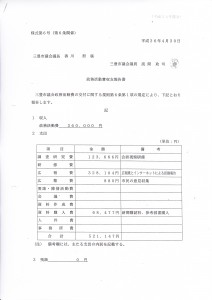三豊市議会の平成26年9月定例会で、私が行った一般質問の報告をします。今回は、2件のうちの1件目 『「子育てするなら三豊が一番!」への再挑戦について』 です。
【質問】
子ども・子育て支援新制度が平成27年度から実施されるべく、制度設計が進められている。今議会においてもそれに係る条例案が上程され審議されるが、その内容は、認可保育所と公立施設が対象となっているようだ。一方、これまで、市の子育て支援のキメ細かいサービス提供を担ってきた認可外保育所については、ほとんど触れられておらず不十分のままだといえる。市はこれまで 「子育てするなら三豊が一番!」 を掲げ支援の充実に取り組んできたが、近隣自治体も子育て支援強化に向け、認可外保育所に対し利用者への保育料補助や施設補助等を実施するなど、積極的な子育て支援施策に取り組んでいおり、市の掲げた重点プロジェクトである 「子育てするなら三豊が一番!」 の看板は色褪せたように感じる。これまで公立保育所で全ての保育ニーズに応えてきたとはいえず、認可外保育所の役割は大きいものがあると考える。子育て支援施策における認可外保育所の必要性と、子ども・子育て支援新制度をきっかけとして、「子育てするなら三豊が一番!」 への再挑戦の考えを問う。
【答弁】
三豊市では、「子育てするなら三豊が一番!」 を重点プロジェクトと位置づけ、早くから子育てしやすく住みやすい環境づくりのため施策を重点的に進めてきた。しかしながら、他の自治体でも子育て支援施策の重要性を認識し、認可外保育所やそこで保育を受ける家庭に対する支援を行う自治体も出始めている。子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、認可保育所といった国の定める設置基準を満たしている施設に関して、その在り方を示すものである。しかし、三豊市の保育行政は、市立保育所と認可外保育所が連携を図り推進してきており、認可外保育施設が担ってきた役割は大きいものがあるため、これからの新制度の下においても引き続き重要な役割を担ってもらうこととなる。現在、新システムについては、子ども・子育て会議を開催して、次年度以降の計画を検討しているところだ。今後は、認可や認可外等の設置形態にかかわらず、支援の方策を検討していく必要があると考える。これからも引き続き、「子育てするなら三豊が一番!」 を重点施策として取り組み、社会全体で子育て家庭を支える環境づくりのため、認可外保育施設とも連携を図りながら、子育て支援のさらなる充実に努めていく。
次回は2件目の報告をします。