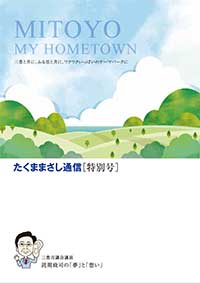三豊市誕生以来の5期目となる、三豊市議会議員選挙の公示日(1月23日・土)が近づく慌ただしい日々ですが、任期中のことは任期中に済ませることに尽きます。任期最後となる昨年12月の 令和3年第4回定例会 における一般質問の報告をします。
「視覚障がい者支援センターの方向性について」
質問 令和2年3月31日の「三豊市障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」制定をきっかけに、視覚に障がいのある市民有志によって、日常生活支援となるタブレット等の先端ICTツールを活用した勉強会が、MAiZMの協力を得て行われてきた。その成果と実績によって、令和3年度に三豊市福祉事務所の支援で『視覚障がい者支援センターひかり』が結成され、視覚に障害を持つ当事者自らによって運営と活動が始められている。
市内には視覚障害で手帳所有者は約150人だが、参加者はその一割ほどにとどまっている。この現状は、視覚障がい者支援を行う支援センター機能を果たす拠点がこの地域にないからだと考える。「ひかり」を核にした西讃地域の視覚障がい者支援センター充実に向けた考えを問う。
答弁 条例制定により、情報の取得及びコミュニケーションの困難の有無によって分け隔てられることがない共生社会を実現することを目指し、障害の特性に応じた支援策を進めている。まだ一割程度の参加者数だが、回を重ねるごとに少しずつ増えつつある。また、香川県眼科医会が発行するチラシに掲載していただけることとなり、活動が徐々に浸透し、認知されてきている。
先ず、組織の基盤を固め、目指す方向に進んでいけるよう当事者の方々と相談しながら、今後も継続した支援に取り組んでいく。
再質問 私は、令和2年度のICT研修会の立ち上げから活動の様子を見てきた。障害を持つ方々の中においても、視覚に障害を持った人が最も社会参加に取り残されているのではないかと痛感した。
今、社会を豊かにする科学技術は飛躍的に進歩し、ICT、AI技術の発達で、視覚障がい者の皆さんの目の代わりができるツールが普通に使える時代になってきた現実がある。一方、その情報が視覚障がい者の皆さんに届きにくい環境のままであるという現実がある。この二つの現実を有機的に結びつけるためにも、西讃地域の視覚支援センターが必要だと考える。
ICT研修会に加え、ここで取り組むべき具体的事業は ①同行援護事業 ②相談支援事業 ③普及啓発事業 の3点だ。これを実現するためには、独立した本格的法人格の取得とスタッフの確保、拠点場所が必要最低条件だろうと考える。
答弁 人が受け取る情報のうち8割は視覚からの情報といわれている。その意味するところは、視覚に障害を持つ方が情報の取得に苦労し、生活困難を抱えているかが分かる数字といえる。
今、「ひかり」では、目が見えなくてもスマートフォンやパソコンなどのICT機器を使うことによって世界が広がることを一人でも多くの人に伝えようと活動されている。また、外出の同行をするヘルパーの養成や相談、普及啓発事業等を計画しているとも聞いている。
「ひかり」が、いずれは視覚障害を持つ人の拠り所となれるよう、その支援の在り方を検討するとともに、障害のある人もない人も、だれもが安心して暮らすことのできる社会の実現を目指して取り組んでいく。
再々質問 企業の存在意義に関する記事を見た。マイクロソフトの視覚障害者向けアプリが、いかに企業の存在価値に根差したものなのかを伝えるものだった。マイクロソフト再興の立役者、サティア・ナデラCEOは、「地球のすべての個人とすべての組織がより多くのことを達成できるようにすることが企業の存在意義だ」といい、その象徴の一つが視覚障害を持ったエンジニアが開発した視覚障害者向けアプリだという。
スマートフォンのカメラを周囲に向けると、状況を読み取り音声で説明してくれるもので、目の代わりをするのだ。これまで諦めていたことが、最先端技術を使えば可能となる時代となっている。その可能性の恩恵を広く視覚障がい者の皆さんに知っていただき活用し、新しい豊かな生活を享受してほしいと願っている。福祉行政の存在意義はそこにあると思う。
答弁 三豊市重度障害者日常生活用具給付実施要項に基づき、情報・意思疎通支援用具を給付しているが、給付対象用具が、急速に進歩する技術に追い付いていないというのも現状だ。
制度の拡充を検討しているところであり、当事者の方の意見を聞きながら、視覚に障害のある方の日常生活がより豊かなものとなるよう支援していく。
以上で、今期最後の一般質問報告を終わります。