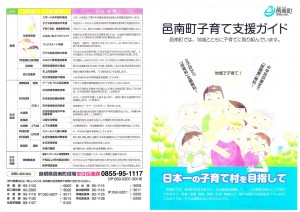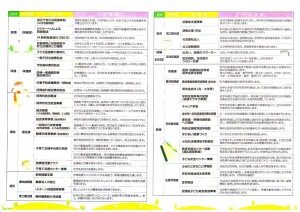平成27年第1回三豊市議会定例会が3月2日(月)から26日(木)までの25日間の会期で開催されています。来年度の予算案を主な議題とする3月議会は、今年度最終となる補正予算や、来年度から施行される条例の制定及び改正の議案など54件が審議されています。
3月6日(金)には、平成26年度の補正予算案11件、及び地方創生関係の補正予算に係る議案が1件、可決されました。 「議案第24号 三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置条例の制定について」 国の総合戦略が定める政策分野にそって、市の目標設定や施策の効果の検証を目的に設置する。
3月12日(木)と13日(金)に開催された3常任委員会では、付託案件について審査されました。
「議案第23号 三豊市公文書等の管理に関する条例の制定について」 公文書管理法に則り行政文書の管理の統一的ルールを定めるとともに、文書館との連携の下に歴史公文書の適正な保存を行うため。
「議案第25号 三豊市基金の処分の特例に関する条例の静定について」 ペイオフに対応するため、基金を取り崩し相殺できるようにするため。
「議案第26号 三豊市がんばる企業応援事業補助金審査委員会設置条例の制定について」 応募申請内容を厳正かつ公平に審査するため。
「議案第27号 三豊市ものづくり大賞審査委員会設置条例の制定について」 功績のあった中小企業等を表彰するにあたり、厳正かつ公平に審査するため。
「議案第28号 三豊市歯と口腔の健康づくり推進条例の制定について」 国の法及び県の条例に基づき、市においても推進するため。
「議案第29号 三豊市事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金審査委員会設置条例の制定について」 事業所からの子育て支援施設整備の提案に対し、補助金交付審査を行うため。
「議案第30号 三豊市子どものための教育・保育給付に関する条例の制定について」 子ども・子育て三法により、利用額や保護者の報告義務等の罰則を定めるため。
「議案第31号 三豊市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について」 新教育委員会制度施行にともない、常勤の特別職となり職務専念義務が規定されるため、教育長の職務の一部の免除を定めるため。
「議案第32号 三豊市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について」 いじめ防止対策推進法制定に伴い、対策連絡協議会を置くとともに、いじめ問題調査のため調査委員会及び再調査委員会の設置を定めるため。
「議案第33号 三豊市防災会議条例の一部改正について」 危機管理課設置のため、総務部総務課長を危機管理課長に改めるため。
「議案第34号 三豊市消防団条例の一部改正について」 7方面隊運営費を新たに設けるため。一人当たり2,000円/年を支給する。
「議案第35号 三豊市職員の給与に関する条例の一部改正について」 人事院勧告により、医師の地域手当支給率及び医師の通勤手当、管理職員の特別勤務手当の支給、給料票の改正のため。
「議案第36号 三豊市詫間町松崎コミュニティセンター条例の一部改正について」 指定管理できるようにするため。
「議案第37号 三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例の一部改正について」 指定管理できるようにするため。
「議案第38号 三豊市宝山湖公園条例の一部改正について」 芝生広場の利用料を減額するため。中学生以下を4,000円から2,000円に、一般を8,000円から4,000円へ。
「議案第39号 三豊市防災センター設置条例等の一部改正について」 旧町時代から使用されていた住所表記を訂正するため。
「議案第40号 三豊市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正について」 山本町、財田町のし尿が平成27年4月1日より他町と同様の処理となるため。
「議案第41号 三豊市介護保険条例の一部改正について」 保険料率を7段階から9段階とし額を定めるため。
「議案第42号 三豊市福祉センター条例の一部改正について」 旧町時代から使用されていた住所表記を訂正するため。
「議案第43号 三豊市手数料条例の一部改正について」 鳥獣保護に係る法律名が変わることにより、それに改めるため。
「議案第44号 三豊市農村環境改善センター条例及び三豊市市営住宅設置条例及び管理条例の一部改正について」 旧町時代から使用されていた住所表記を訂正するため。
「議案第45号 瀬戸グリーンセンター更新工事事業に伴う負担金平準化基金条例の廃止について」 整備に係る負担金を一括払いすることで事業が完了するため。
「議案第46号 三豊市仁尾町ふれあい健康会館条例の廃止について」 仁尾町福祉会館取り壊しのため、施設内にあった児童館が移転利用できるようにするため。
「議案第47号 『子ども・子育て支援法』及び『子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律』の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」 子育て支援法等施行及び福祉関連法改正に伴い、改正4件と廃止1件のため。
「議案第48号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」 地方教育法の改正に伴い、教育委員会組織変更のため。
「議案第49号 香川県広域水道事業体設立準備会の設置について」 県内6市8町(坂出市と善通寺市は不参加、直島は岡山県から送水)で協議会を設置するため。
「議案第50号 指定管理者の指定について(三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設)」 たかせ天然温泉を、(株)創裕に引き続き指定管理委託するため。平成27年4月1日~平成32年3月31日までの5年間。
「議案第51号 指定管理者の指定について(三豊市高瀬町産地形成促進施設」 心泉市たかせを、(株)創裕に引き続き指定管理委託するため。平成27年4月1日~平成32年3月31日までの5年間。
「議案第52号 指定管理者の指定について(三豊市粟島海洋記念公園)」 ルポール粟島等を、(株)創裕に引き続き指定管理委託するため。平成27年4月1日~平成32年3月31日までの5年間。
「議案第53号 指定管理者の指定について(三豊市山本町山地直売所)」 (有)山本ふれあい市に引き続き指定管理委託するため。補助金適化法により平成27年4月1日~平成29年3月31日までの2年間。
「議案第54号 指定管理の指定について(三豊市財田町土づくりセンター)」 JA香川に引き続き指定管理委託するため。平成27年4月1日~平成37年3月31日までの10年間。
なお、平成27年度予算案は議会開会中に開催される予算特別委員会において、審査することとなっています。
全議案の採決は3月26日(木)の、議会最終日に行われることとなります。