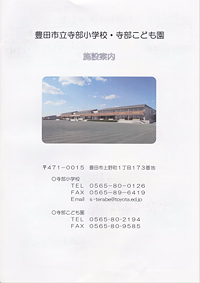平成28年9月定例会で審議された29議案の内、「平成27年度決算関係」以外の「補正予算関係と他議案」について報告します。
<補正予算関係>
【一般会計】
補正額は8億59,816千円で、補正後予算額は317億65,198千円となります。
「施設管理課」 621千円 宝山湖公園管理運営事業471千円他
「企画財政課」 6億34,866千円 基金管理事業6億34,000千円(積立金)、三豊中学校交付税配分866千円
「田園都市推進課」 705千円 公共施設再配置事業486千円他
「環境衛生課」 1億29,265千円 火葬場建設事業1億29,194千円他
「水処理課」 6,384千円 集落排水事業特別会計繰り出し金5,958千円他
「バイオマスタウン推進課」 3,651千円 バイオマスタウン資源化センター事業(事業モニタリング計画策定支援事業2,268千円、法律的支援指導業務1,383千円)
「健康課」 727千円 国民健康保険事業610千円(繰り出し金)他
「介護保険課」 12,252千円 介護保険事業特別会計繰り出し金10,399千円、地域介護・福祉空間施設整備事業1,853千円
「子育て支援課」 5,760千円 予防接種事業
「農業振興課」 862千円 有害鳥獣対策事業
「土地改良課」 1,830千円 土地改良施設維持管理費1,620千円他
「建設課」 27,900千円 市単独道路橋梁新設改良事業22,900千円、市管理河川維持事業5,000千円
「建築課」 9,872千円 空き家対策事業
「港湾水産課」 4,600千円 漁港管理費2,100千円、港湾管理費2,000千円他
「教育総務課」 18,988千円 教育総務管理事業(三豊市観音寺市学校組合負担金)
「生涯学習課」 4,005千円 公民館活動推進事業3,925千円(工事請負費等)他
「人権教育課」 1,296千円 集会所管理運営費(施設修繕料)
【特別会計】
8つの特別会計の補正額合計は1億28,003千円となり、補正後予算額は193億47,003千円とます。
①国民健康保険事業特別会計 3,658千円 補正後99億83,658千円
②国民健康保険診療所事業特別会計 4,699千円 補正後1億69,699千円
③後期高齢者医療事業特別会計 1,588千円 補正後9億35,588千円
④介護保険事業特別会計 1億8,039千円 補正後76億98,039千円
⑤介護サービス事業特別会計 138千円 補正後1億6,138千円
⑥集落排水事業特別会計 7,518千円 補正後1億99,518千円
⑦浄化槽整備推進事業特別会計 426千円 補正後2億31,426千円
⑧港湾整備事業特別会計 1,937千円 補正後22,937千円
【企業会計】
2つの企業会計はいづれも補正はありません。
<その他議案>
「議案第95号・96号 市道の路線認定について(北北浦線・詫間339号線)」 2路線とも認定された。
「議案第97号 財産の取得について(三豊市情報セキュリティ強靭化に係る機器)」 一般競争入札で(株)富士通四国インフォテックに78,679,800円で決定した。
「議案第98号 財産の取得について(雇用促進住宅)」 高瀬宿舎及び付属建物(鉄筋コンクリート造5階建て2棟・3,429.72㎡)を、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、38,391,300円で取得した。
以上で、平成28年9月定例会の報告を終わります。